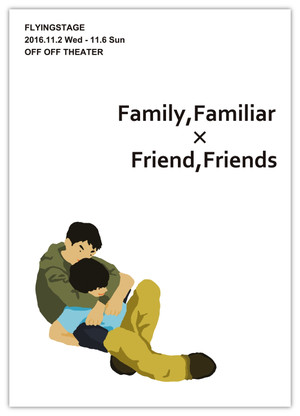かつて、10代でロックと出会って間もなくして、「自分の好きな音楽について自分が書いた文章が音楽雑誌に掲載されること」が、私の夢になった。そして、20歳の春、『rockin'on JAPAN』という雑誌に、あるバンドについて書いた私の文章が掲載された。その文章は、b-flowerというバンドの『ペニーアーケードの年』というアルバムについて書いたものだった。
それからずっと、自分の好きな音楽について文章を書くことは、私の夢であり続けている。だから、自分の好きなバンドやアーティストについての文章を書いてブログを更新するたびに、私は夢を叶えている。そして、20歳のあの春から長い月日が流れ、今こうしてb-flowerのベスト盤について文章を書くことで、私はまた一つ夢を叶えることになる。
1. 揺るぎない個性と進化(深化)
出会いは、偶然ラジオから流れてきた“April Rain”。イギリスのインディーズギターバンドやネオアコースティック直系のメロディと、英米文学をも髣髴とさせる文学的な歌詞というバンドの魅力もさることながら、その奥に透けて見える「自分達の美意識は1ミリも譲らない」という静かな意志に「ロック」を感じた。繊細で美しい音楽であること自体による「世界」に対するプロテスト――その印象は、このベスト盤を通して改めてb-flowerの歩みに触れて、より確かなものになった。そして、ほぼリリース順に配置された曲順による2枚組のこのベスト盤を聞くと、揺るぎない個性を保ちながら進化(深化)を遂げてきたバンドの姿が浮かび上がってくる。
主に本作Disc1収録の1stEP『日曜日のミツバチ』(1990)から3rdアルバム『World's End Laundry』(1993)までは、バンド名の由来である詩人リチャード・ブローティガンや、1stアルバムの表題曲“ペニーアーケードの年”の下敷きとなっているスティーブン・ミルハウザーの小説『In The Penny Arcade』にも通じる、文学的な想像力によって「ここではないどこか」を夢見るような世界観が色濃い。けれど4thアルバム『Groccery Andromeda』(1995)から兆した変化は、Disc2収録の5thアルバム『CLOCKWISE』(1996)以降にはっきりと表れてきた。『CLOCKWISE』以降には、「繊細で文学的なギターバンド」というイメージに囚われずにバンドの元々の音楽性の幅広さを生かし、その音楽によって現実から逃避するよりもむしろそれを自分なりに描いていこうとするしなやかな力強さがある。そして、その力強さの奥には、現実の日常的なありふれてさえいる風景を「文学」として成り立たせてしまう詩才がある。“臨海ニュータウン”のコンビナートに沈む夕日や“明星”の川の土手を走るバスは、見慣れた風景の中に発見する美しさと優しさが、舟の錨のように、自分というちっぽけな存在をこの世界につなぎとめてくれるのだと告げているようだ。
向こうの土手を バスが1台
うろこ雲から 星がのぞいて
涙がこぼれそうさ すべてが愛しくて
川の泥に眠る 古い思い出のように
(明星)
Disc2の終盤に収められた2ndアルバム収録の“動物園へ行こうよ”の2014年ヴァージョンが、「逃避の歌」に聞こえないのは、そうしたバンドの進化(深化)に重なっているように思う。“日曜日のミツバチ”の印象が強い人にこそ、本作のDisc2を聞いてほしいと思う。
2. 詞の中の野性(野生)
このベスト盤を聞いて、改めて八野英史の詩才について考えた。心が揺れるフレーズをあげればきりがない。その中でも改めて印象に残ったのは、声優の国府田マリ子に提供した“コバルト”(セルフカヴァー)の中このフレーズ。
耳たぶをぶつけあって笑ったり 恋の深みを泳ぐよ
いつかは実る花のようにね 花のようにね
くちびるの端っこでキスをして 揺れる景色を見ている
僕らは蒼い風のようにね 風のようにね
(コバルト)
その可憐なメロディとアレンジも含めて、うまく言葉にならないまま「見事だなぁ」と溜息をつくしかなかった。それほどに、静かに感動した。
八野英史の詞は、ロマンチックではあるけれど、感覚的というよりは写実的で、抽象的というよりは具体的なのだと、発見した。特に、自然や身体という野性(野生)――移ろいやすく微細で周縁的なそれら――が詞の中にさりげなく織りこまれることで、その風景が微かに生々しく感じられところに、テクニックを超えた詩才というものを感じる。そして、その詞と同じく、あるいはそれ以上に「歌う」メロディとバンドのアレンジが、b-flowerの音楽を<嘘みたいにキレイな色>(永遠の59秒)にしている。
3. 美しい曇り空
b-flowerのCDジャケットは、これまでもずっとその音楽のイメージを端的に象徴するような印象的なものばかりだった。そして、今回のベスト盤のジャケット。一目見て「あぁ、b-flowerだ!」と感激した。遊園地と、曇り空――b-flowerには曇り空がよく似合う。b-flowerの音楽に出会ったことで、私は「曇り空の美しさ」を感じるようになった。
思えば、2ndアルバム『太陽を待ちながら』のジャケットや表題曲だけでなく、“日曜日のミツバチ”や“動物園へ行こうよ”など、b-flwerの曲では、曇り空が印象的に描かれている。
寒そうな冬の海 今はもう 君と僕ふたりきり
変わらないスピードで 言葉交わしては
明るい灰色の空を見る
(North Marine Drive)
この詞にあるように、b-flowerの歌う曇り空は、単なる灰色の空ではないということ。明るい青空ばかりではないという苦い現実と、その空の向こうに太陽があるという信頼と、その空の向こうから再び太陽が顔をのぞかせるという予感――b-flowerは、これらを美しく、驚くほど繊細で鮮やかな色使いで歌うことができるバンドなのだということ。その意味でも、やはりこのバンドは唯一無二の存在だと思う。
この文章の冒頭で、私は、この文章を書くことで「また一つ夢を叶えることになる」と書いた。そして、この文章は私にとっては「一つの夢」であると同時に「一つの奇跡」でもあるように感じている。長い時間を通して、b-flowerの音楽が変わらずに私の心に届くということ――その「奇跡」に心から感謝したい。