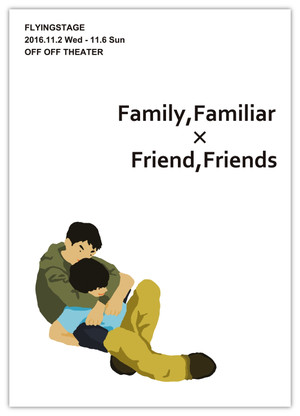2013年にリリースされたファン投票によるベストアルバム『イエモン―FAN'S BEST SELECTION―』の収録曲を、再集結したザ・イエローモンキーが新たにレコーディングし直したベストアルルバム『THE YELLOW IS HERE』。タイトル通り、イエローモンキーが現在進行形としてのロックバンドであることを、「イエローモンキーここに在り」ということを証明したアルバムになっている。リリースを知った当初は、正直に言うと、過去のベストアルバムを新たに録音し直すということの意味を掴みあぐねる感じがあった。けれど、このアルバムを一聴して、このアルバムの意味がすとんと胸に落ちた。
このアルバムを聞くと、ザ・イエローモンキーが、「ザ・イエローモンキー」の最も熱烈なファンであり、最も厳しい批評家であるということが伝わってくる。その深い愛情と鋭い批評性によって「名曲」を単なる名曲ではなく、2017年の現在に活動するバンドの「今の曲」にしているところに、このアルバムの意味があるのだと思う。「懐かしさ」や「感傷」を押しのけて、新しい「興奮」や「感動」が胸を満たしていくところに、このアルバムの意味がある。
再集結後のツアータイトルに掲げられていた「SUPER」の言葉通り、長いキャリアを経てビルドアップして研ぎ澄まされた歌唱力と演奏力によって、どの曲もその魅力と説得力を増している。特に吉井和哉の歌唱力は、2004年の解散前に比べて段違いの安定感と表現力を増している。“JAM”の、力強いようでありながら幼さゆえの純粋さと怯えさえも湛えた歌声は、曲中のあの少年に出会い直したような感動を呼び起こす。
“悲しきASIAN BOY”や“パール”“楽園”“JAM”などの、ほぼ原曲のアレンジ通りにストレートなバンドの演奏を聞かせる曲は、バンドによる楽曲への深い敬意ともに、「ロックバンド」としてのイエローモンキーの逞しさと色気を改めて感じさせる。その一方で、“太陽が燃えている”や“追憶のマーメイド”などの、ストリングスやホーンセクションを豪華に取り入れた曲は、そのアーティスティックな復讐心(特に“追憶のマーメイド”)にニヤリとさせられるとともに、歌謡曲的なキャッチ―さを持ちながらもあくまでエレガントであるところにこのバンドの奥行があるのだと気づかされる。
特に印象的だったのは、“真珠色の革命時代―PERAL LIGHT OF REVOLUTION―”。繊細なストリングスの、細い光の糸が暗闇にすうっと線を引くように始まるイントロを聞いただけで、この曲をこのバンドがどれほど大切にしているかが伝わってくる。サビで繰り返される「Sally, I love you」のフレーズを聞いて、この曲が収められたデビューアルバム『THE NIGHT SNAILS AND PLASTIC BOOGIE(夜行性のかたつむり達とプラスチックのブギー)』がリリースされた15年後、フジロックフェスティバルでの挫折に傷付いた吉井和哉の心を癒したであろうOASISの“Don't Look Back In Anger”でも「Sally」という名前が歌われている(So Sally can't wait〜)ことを思い、不思議な「縁」を感じた。ライブでの、メカラウロコ楽団が奏でる美しいストリングスのアウトロとは対照的な、高揚感がピークに達したところであっけなく幕切れを迎える曲の終わり方が、心の中に言いようもない感傷と感動をかき立てる―余韻は心の中に。
そして、イエローモンキーのバンドヒストリーだけでなく日本のロック史上の名盤でもある『SICKS』の収録曲である“天国旅行”と“花吹雪”。このアルバムでこの2曲を聞いて抱いた感想は、対照的であるようでいて実は同じことを言っている感想だった。“天国旅行”を聞いて「あの『SICKS』の演奏を超える演奏があったのか」と思った。“花吹雪”を聞いて「この演奏を持ってしても『SICKS』のあのテイクは超えられないなんて…」と思った――どちらにしても『SICKS』はやはり奇跡的なアルバムであり、その「奇跡」に比肩しているという点に再集結したイエローモンキーの凄さがあるということ。言い方を変えるならば、『SICKS』の楽曲を新たにレコーディングして原曲に負けないだけの自信と気概があるからこそ、このバンドは再集結したのだということ。
それにしても…と思う。かつて、このバンドが、その後四半世紀を経てもなお新たにレコーディングする価値のある楽曲を生み出し、そしてそれをかつて以上の力強さと美しさで演奏しているということに、驚きと尊敬を感じずにはいられない。
感謝と尊敬と、そして、期待を込めて、12月の東京ドームのライブを待ちたいと思う。

【早期購入特典あり】THE YELLOW MONKEY IS HERE. NEW BEST (『2017 LIMITED SPECIAL SINGLE CD』(新曲「ロザーナ」収録)付)
- アーティスト: THE YELLOW MONKEY
- 出版社/メーカー: 日本コロムビア
- 発売日: 2017/05/21
- メディア: CD
- この商品を含むブログ (9件) を見る