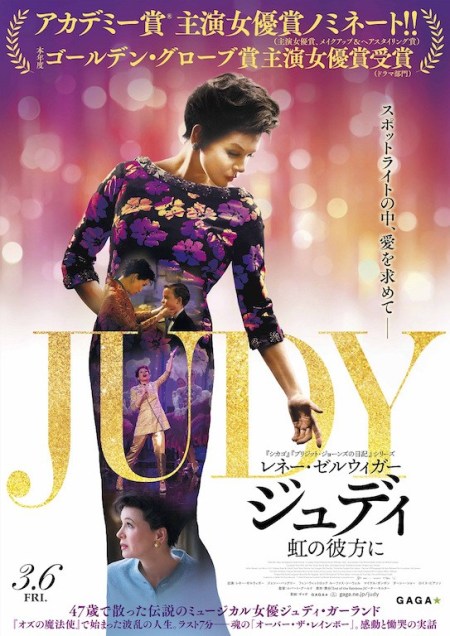映画『オズの魔法使い』で有名なミュージカル女優、ジュディ・ガーランドの伝記的映画『ジュディ 虹の彼方に』を観た。「ショウビジネスの光と影」「大スターの栄光と苦悩」というクリシェに落とし込まれがちな物語ではあるけれど、主人公をスターダムに押し上げた映画スタジオの裏側と晩年のジュディの姿のリアルな描写によって、その物語はクリシェでは割り切れない、複雑で多面的な人物像を描いていた。
静かな虐待
映画は、ジュディの亡くなる半年前のロンドン公演の日々を軸に展開しつつ、トラウマのフラッシュバックのように差し挟まれる少女時代の回想が、薬とアルコールと不眠症でついにはステージをまともに務められなくなってしまう最晩年の彼女の姿を説明していた。
少女時代の場面はすべて、映画の撮影所のシーンで、彼女が撮影所という「檻の中の鳥」だったことを象徴していた。そんな生活への怒りからプールに飛び込んだジュディは解放された表情を見せるものの、それがセットの小さなプールであることが、むしろ彼女の「逃れられなさ」を強調していた。
薬物によって食事と睡眠をコントロールされながら長時間労働を強いられる姿は、「虐待」と言えるものだった。けれど、それは明確な暴力や暴言によってではなく、静かに遂行されていた。ジュディのささやかな反抗に対して、映画スタジオのプロデューサーであるメイヤーは紳士的な態度と諭すような言い回しによって、撮影所以外では彼女は無価値な存在で居場所がないのだという「呪いの言葉」をかけていた。その巧妙な脅しによって、ジュディが謝罪と感謝の気持ちを述べる姿は、虐待と洗脳は一つのことなのだと伝えていた。
映画の終盤、撮影の都合で2か月早まった「16歳の誕生日」に用意された偽物のバースデーケーキとそっくり本物のケーキを前に、嬉しさで胸がいっぱいなのか、食べ方が分からないのか、身体が受け付けないのか、そのいずれでもある様子で、ゆっくりとほんの一かけらのケーキを口に運ぶジュディの姿は、失われた少女時代のほんのわずかの回復とともに、それを完全に取り戻すことの困難を象徴していた。
賢明な母親
映画は、少女時代に背負った負の財産(薬物とアルコールへの依存、不眠症)によって早逝した悲劇の女優という物語をなぞりつつも、彼女のもう一つの顔もまた描いていた。それは、子どもに対する「母親としてのジュディ・ガーランド」の姿だった。
楽屋すらない巡業の開演前に子どもの衣装を整える場面、子ども達を残してロンドンに発つ前のクローゼットの中で抱き合う場面、そして電話ボックスで父(離婚した夫)と暮らす選択を娘から告げられる場面――浮き沈みの激しいステージ上の姿とは裏腹に、母親としてのジュディは一貫して優しく愛情深い態度を貫いていた。
特に印象的だったのは、彼女が子ども達の欲求を決して否定せずに満たそうとしていた姿だった。娘ローナがルームサービスで「ハンバーガーとポテト」を注文した場面と、「眠れない」と起き出してきた息子ジョーイにホットミルクを作ってあげる場面――少女時代の回想では、ダイエットのためにハンバーガーとポテトを食べさせてもらえず、「眠れない」という訴えに大人の都合で睡眠薬を与えられていたこととは対照的に、母親としてのジュディは、彼女が少女時代に受けた仕打ちを子どもに繰り返すことのない、適切な関わりのできる母親だったことが描かれていた。
娘ローナが父親(離婚した夫)の家で暮らしたいと告げる場面は、この映画の中でも最も絶望に満ちた場面であったけれど、涙を押し殺して子ども達の選択を受け入れるジュディの姿は、彼女が「賢明な母親」であったことを証明していた。
別の言い方をするならば、少女時代のジュディが与えられなかったもの(食べたい物を食べる、眠りたい時に寝る、居心地の良い場所で暮らす)を、彼女は自分の子ども達には与えることができていたのだということ。娘ローナが自分にとってヘルシーな暮らし方(母親とではなく父親と暮らす)を選択できたことは、ジュディがそのように選択できる力を娘に育てたのだとも言える。それはちょうど、ステージに上がることの緊張や不安に押しつぶされそうになる母親ジュディとは対照的に、二番目の夫との娘である、若きライザ・ミネリの「(ショーには)不安を感じないの」という屈託のない笑顔からも傍証されていた。
この映画がジュディ・ガーランドの名誉に資するものであるとするならば、その一部は、彼女が「賢明な母」であったことを描いた点にあるのだといえる。
ファンからの贈り物
スターの伝記的映画の中でも、この映画のように、ファンの存在と彼らの力を描いた映画は珍しいのではないかと思う。「希望」というものの得難さがモチーフであるかのようなジュディ・ガーランドの生涯において、ファンの存在が、「彼女の人生には確かに希望があった」ということを証明していた。特に、ロンドン公演に通いつめ楽屋口で入待ち出待ちをするゲイのカップルの姿は、「ファンの人生」におけるスター(推し)の存在のかけがえのなさを体現していた。ジュディから食事に誘われた時の、当てにしていたレストランが閉まっていた時の、そして自作のオムレツが失敗した時の、彼らの狼狽ぶりと慌てっぷりは、スターに対するファンの愛情と尊敬の純粋さと深さを愛おしくかつリアルに映画いていた。
また、ジュディを診察した医師から『オズの魔法使い』のドロシーに憧れていたことを告白される場面。医師の告白に対して「男の子はみんな、おさげ髪が好きなのよ」とかつての自分の人気を「記号として消費されたもの」であるかのように自嘲するジュディ。その後に医師が続けた「犬を大切にしていたから」という言葉を聞いて、診察台に腰かけたジュディが虚を突かれたような表情で足を内股気味にだらんと投げだした姿が姿がとても印象的だった。その姿はまるで「そんなこと言われたのは初めてだわ」と困惑する少女のようだった。
スターが見せていないつもりの、あるいは隠してさえいるつもりの、役柄を超えた、仮面の奥にあるスターの本性を、ファンというものは直観で見抜いているのだろう。ファンとは、スター自身以上にスターを理解しているものなのかもしれない。そして、そうした「理解」もまた、スターがファンから受け取る愛情の一つなのかもしれない。その意味でこそ「ファンはスターの鏡」となり得るのかもしれない。
彼女が掴んだ希望
映画のラスト、度重なるトラブルにより契約が打ち切られたロンドン公演のステージ袖で、ジュディは「1曲だけ歌いたい」とステージに上がる。強いられ、騙され、めだめすかされてではなく、自らが望んでステージに向かう彼女の姿に、少女時代の回想が重なる。ジュディの記憶では「ふられた」相手である、ミュージカル映画の相手役ミッキーの誘いを断って、出番の終わったステージに向けられる拍手喝采に微笑むジュディ。その笑顔は、彼女の少女時代の全てが悲劇だったわけではなく、映画やショーの中で彼女自身が掴んだ希望も確かにあったことを伝えていた。
だからこそ、最後に歌われた“Over The Rainbow”の歌唱シーンは、圧巻であると同時に、この歌唱の半年後に訪れた彼女の人生の終わりのとのコントラストを強めていた。葬送曲のような静かなエンドロールは、希望と絶望の両方を舌の上にのせて味わうような、なんともいえない美しさと切なさの余韻に満ちていた。