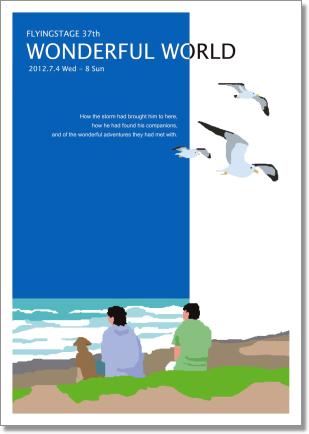3年ぶりに観た劇団フライングステージのお芝居は、何重にももつれてからまった、ほどこうとするとかえってからまってしまう「家族」という糸の結び目が少しずつ緩んでいくようなお芝居だった。
物語は2011年4月から2012年4月の1年間。東北の由緒ある造り酒屋の三兄弟の長男である主人公修一は、かつて「ゲイであること」をカミングアウトして父親に勘当され、家を出た。2011年3月11日を契機に、疎遠になっていた家族の物語が再び動き出す。
物語のほぼ全編を通して、常にどこか憂いを帯びた修一の表情が印象的だった。それは、自分より先に家族にカミングアウトした兄(修一)に「ずるいよ」と激しく憤る三男や、父親となることを先延ばしにして妻に中絶を求める次男の、身勝手ではあるけれど自分自身の欲求に素直な姿とは対照的だった。気がつけば、修一の欲求は何なのだろうと考えながら舞台を観ている自分がいた。
物語の後半、母親が父親に会いに実家に帰ってきてほしいと息子の修一に迫る場面。物語のなかで唯一、修一が声を荒げたこの場面で初めて、彼の欲求が露わになったような気がした。
実家に帰ってきてほしいという母親の願いを一通り聞き終わった後、修一はその申し出を拒み、震災によって家族の絆が再生されるという幻想を疑う。一方の母親は、被災地支援の名を借りて自分自身を救おうとする息子の欺瞞を突く。真っ向からぶつかるというよりも、思いがけずすれ違ってしまう母親と息子のその心の底には深い悲しみがあるのだと思った。彼らの欲求はその悲しみを癒すこと、互いに許し合うことなのかもしれないと思った。
息子に期待を裏切られた母親の悲しみと親に受け入れてもらえなかった息子の悲しみが「対決」するこの場面は、震災以降に再発見された「他者とともに生きること」や「他者のために生きること」という存在理由ですら癒せない家族の傷を示すと同時に、「震災」というテーマを呑み込む「家族」というもののどうしようもない複雑さをも表していた。この物語が、震災を機に家族の「絆」を取り戻す再生の物語のようでありながら、家族の間に横たわる未解決の問題に向き合う物語でもあることが伝わってきた。
そんなふうに、家族のいかんともしがたい厄介さが描かれる一方で、物語の端々で登場する共食のエピソードが印象的だった。餃子、バーベキュー、流しそうめん、芋煮会…と、物語のなかで登場人物達が誰かとともに食事を作り、誰かとともに食べようとすることのなかに、「家族」と呼べる親密な関係や交流が立ち現れていた。
主人公が家族を失う発端となった食卓が、新たな家族を生み出すということ。人はある食卓を捨てても(食卓を追われても)、またどこかの食卓に辿りつけるのかもしれない。その意味で、劇団主宰者で作・演出を手掛ける関根信一が演じていた主人公の大家である幸枝がいつも主人公宅に食べ物(山菜、餃子、関西焼き)を持って現れていたのは、象徴的だった。
物語の最後では、祖母の死*1や次男の妻の出産を機に、主人公と父親との確執はどこかなし崩し的に雪解けを迎える。生と死という抗いようのない出来事を通して家族が再生していく過程は、「コントロールし得ないものとしての家族」を浮かび上がらせていた。ゲイの息子を勘当した父親も、嘘をついて(芝居をして)でも息子を実家に帰ってこさせようとした母親も、自分を勘当した父を遠ざけ続けた息子も、それぞれがそれぞれに自分の願う家族のあり方を懸命にコントロールしようとしていただけなのかもしれないということ。そして、それぞれがそれぞれにそのコントロールを手放したときに、彼らの距離は驚くほどあっけなく再び近づくのかもしれないということ。
選ぶのではなく任せる、掴むのではなく手放す――「家族」というこんがらがった糸は、ほどくのではなくほどけるものなのかもしれない。
いいお芝居だった。*2。