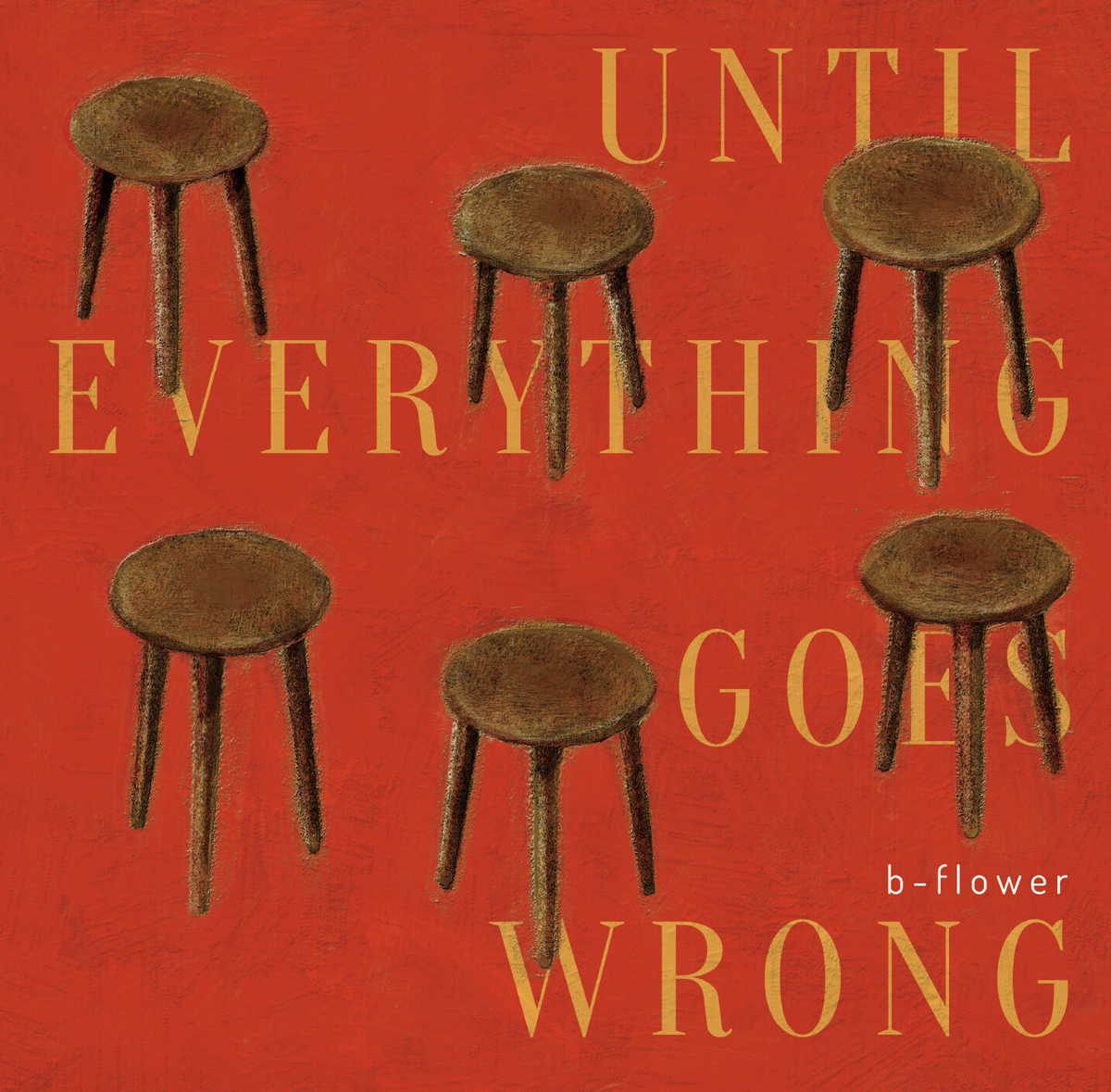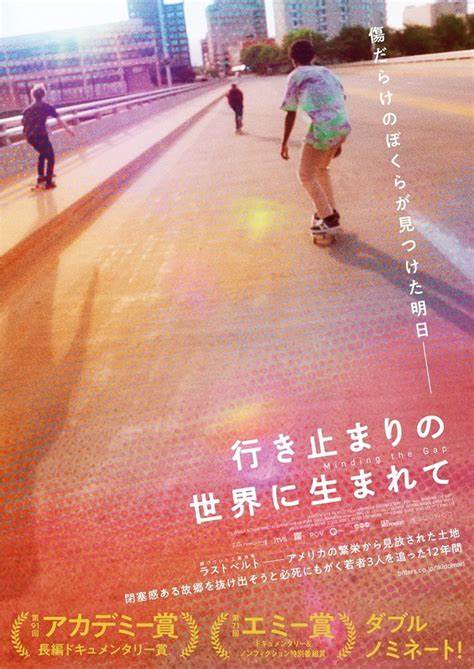吉井和哉の笑顔が少ないライブだった。印象に残ったのは、涙こそ流れてはいないもののほぼ泣き顔で“JAM”を歌う姿や、ライブの最後の“プライマル”を歌い終わって歯を食いしばりながらマイクをマイクスタンドに戻す姿だった。でも、だからこそ、この日のライブにはこのライブをやる意味と価値が、バンドにもファンにもあったのだと思う。
本来ならば、2020年4月にザ・イエローモンキー結成30周年のドームツアーの有終の美を飾る東京ドーム公演が行われるはずだった。しかし、新型コロナウイルス感染症の影響によりライブは延期の後チケット払い戻しとなり、代わりに新規4公演(東京ドーム、横浜アリーナ、代々木第一体育館、日本武道館)が発表された。このライブはその最初のライブであり、かつ新型コロナウイルス感染症による一連の自粛後、大規模会場での最初の有観客公演となった。バンドの歴史が世の中の大きな流れと交錯する「奇縁」に、「イエローモンキーらしさ」を感じた。吉井和哉も少し笑いながらMCでそんな感じのことを言っていた。
約5万人の収容人数に対して客席を1万9000人に限定するともに、入場にあたっては「指定時間ごとの分散入場」「接触確認アプリ『COCOA』の画面表示」「スプレーによる手指消毒」「サーモグラフィによる検温」「足ふきマットによる足裏消毒」「自席でのドームアラート登録」とできる限りの感染防止策が取られていた。観客側はそれらに半ば適応しているようで入場はいたってスムーズだった。だからなのか、1曲目の“真珠色の革命時代”を慎重に丁寧に歌い始めた吉井和哉の表情を見た時、この状況下でのライブは、観客よりもむしろアーティストにとって試練なのかもしれないと思った。それは観客数や歓声が制限されているという物理的な条件によるものという以上に、ロックバンドとしての、歌い手としての存在意義という問いに向き合わざるを得ないからなのかもしれない、と。だから全客席に配布された一斉制御のLEDライト「FreFlow(フリフラ)」や、声を出せない中で声を届ける企画「Sing Loud」(予め録音されたファンの音声を演出に使う、胸の高さにグッズタオルを掲げる)が新しいライブの可能性を感じさせつつも、それがこれからのライブにどう影響していくのかは未知数な気がした。
とはいえ、センターステージで、会場を埋め尽くす真っ赤なFreFlowの灯の海の中で歌われた”JAM”は、どこか「荘厳さ」さえ感じさせ、深く心に届いた。東京ドームでこの曲を聞くのは5回目だけれど、過去に聞いたどの”JAM”とも違う意味が、渾身の歌唱と演奏から立ち上がってくるようだった。
昨年12月の名古屋ドーム、今年2月の京セラドームとセットリストや構成は重なるものの、チンドン屋さんやブラスバンドと華やかに共演した“DANDAN”は歌われず、結成30周年の祝祭ムードよりも、未来が見えず答えが出せない状況に挑むような印象を残すライブだった。そのせいか“Four Seasons”“パンチドランカー”“パール”といった挑み、闘おうとしている曲がいつも以上に尖った迫力を帯びて聞こえた。
そして、一番印象残ったのは、アンコールの“悲しきASIAN BOY”が終わった後間髪入れずに始まった、“プライマル。”。2001年の活動休止後にリリースされた解散前最後のシングル曲であり、2016年の再集結後のライブで最初に演奏された曲――別れと新たな旅立ちを歌ったこの曲は、意外ではあったけれど再集結後の「シーズン2」を締めるにふさわしいと感じた。そして同時に、“悲しきASIANBOY”でライブの大団円を迎えるという予定調和を打ち破るという意味で、この選曲にはイエローモンキーの「新しい季節」「次の一歩」を予感させるものだった。
MCの中で吉井和哉が悔いていた2001年の東京ドーム公演時よりも、歌唱力、演奏力、メンバー間の結束、ファンとの信頼関係など全てがパワーアップして、まさに「脂ののった」バンドの状態であるにもかかわらず、というよりもだからこそ、結成30周年の東京ドーム公演をコロナ禍で行うことの複雑なムードとのせめぎ合いが、このライブの感動を生々しいものにしていた。そして、向かい風の時の方が、風を受ける横顔が無防備に額をさらすように、そのバンドの本質が剥き出しになるのだとしたら、イエローモンキーならばきっとまたそれを乗り越えていくのだろうという気もした。
同じ時代に生きて、同じ空間に集うことの意味を考えたライブだった。と同時に、イエローモンキーと同じ時代に生きて同じ風の中を生きていることに感謝したいと思った。
THE YELLOW MONKEY セットリスト(2020/11/03)
真珠色の革命時代~Peal Light of Revolution~
追憶のマーメイド
SPARK
Ballon Ballon
Tactics
球根
花吹雪
FOUR SEASONS
Foxy Blue Love
SLEEPLESS IMAGINATION
熱帯夜
BURN
JAM
メロメ
天道虫
パンチドランカー
LOVE COMMUNICATION
バラ色の日々
SUCK OF LIFE
パール
未来はみないで
―encore-
楽園
ALRIGHT
悲しきASIANBOY
プライマル。
追記1:ドーム公演での“球根”は、どれも素晴らしかった。なぜ、この曲だけが唯一大型スクリーンで吉井和哉の顔を映さないのか、なぜ吉井和哉はこの曲の最後に一礼するのか、その意味がわかるような気がした。
追記2:MCで吉井和哉は、今回の東京ドーム公演には、2001年の活動休止前の東京ドーム公演の「借り」を返したいという思いがあったということを話していた。2017年の東京ドーム2days公演の素晴らしさを「スキップ」しているところが、吉井和哉らしいと思った。バンドヒストリーに関して、吉井和哉は時に「修正」するように見えることがあるけれど、それもまた「真説」なのだろう。